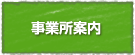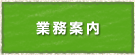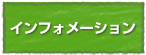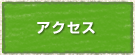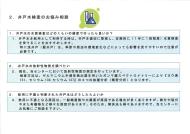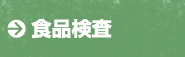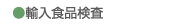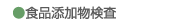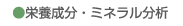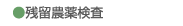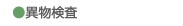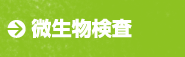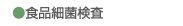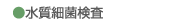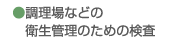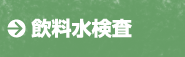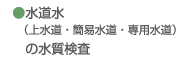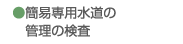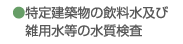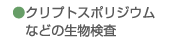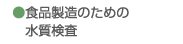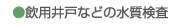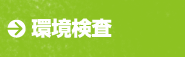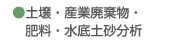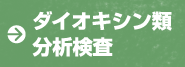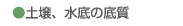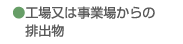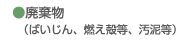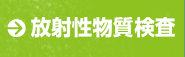情報広場
※ブルダウンからカテゴリを選択していただくと、カテゴリを絞って、情報を閲覧することができます。
水の話近代水道とは?2014-01-28
みなさんは、『近代水道』という言葉をご覧になってどのようなものを想像するでしょうか。これは将来開発される新たな水道技術などではなく、ふだんから蛇口などを通して飲み水や洗濯などに使っている上水道のことです。

『近代水道』の定義は、外部から汚染されないように鉄管や近年ではステンレス管などの閉じた導管を使い、ろ過・消毒などを行った人の飲用に適する水を、圧力をかけて常に供給する施設の総体のこととされています。
日本における最初の近代水道は、明治20年に横浜市に布設されました。 | 
それまでに水道と呼ばれるものは、木製の樋(とい)に川の水を引き込み、その水を炭や砂でろ過して使っていたという記録があります。
ただし、この木樋(もくひ)水道は、木管が腐って穴が開き水が漏れたり、外部からの汚水が浸入することがあるため水質には問題があり、コレラなどの伝染病を広げる一因となっていました。 |

日本の『近代水道』布設の目的の一つは、コレラ菌など伝染病の感染を防ぐことにありました。
明治10年9月長崎に来航したイギリスの商船からコレラ菌患者が発生し、横浜市でも明治10年、12年、15年、19年にコレラが大流行しましたが、近代水道が布設された明治20年以降は横浜市内のコレラ感染者数は10人以下に抑えられています。
『近代水道』の普及によって清潔な飲料水を確保できるようになり、コレラ、赤痢、腸チフスの水系伝染病の発生を防ぐ事が出来るようになりましたが、他にも役立っていることがあります。 |

それは、近代水道を利用した消火活動です。ポンプもない時代では技術的にも限界があり、消防活動の中心は、火災周辺の住宅を破壊して延焼を防ぐ破壊消火(除去消火法)であり、消防技術としては龍吐水や水鉄砲など小規模の火を水で消すため道具が作られた程度でした。
現在では、水道管の布設に伴い北九州市内では主に地下式消火栓が設置され、火災発生時の際の消火活動にも『近代水道』が役立てられています。 |

『近代水道』の普及により、わたしたちは蛇口を開ければ安全でおいしい水を飲むことが出来るようになりました。しかし、飲料水の源となるダムや河川の環境が悪化すれば、飲料水の水質にも影響するかもしれません。これからも安全・安心な水を確保するために、わたしたち自身が水源環境の保全に努めていかなければいけません。
当センターも安心して水を飲んでいただくために水質検査の専門家として、水の健康を維持するお手伝いをさせていただきます。 |
|
|
|
水の話プール水の衛生管理2013-08-16
8月に入りいよいよ夏本番!連日猛暑が続いております。
少しでもこの暑さを和らげるためにプールに行かれる方も多いのではないでしょうか。
公益財団法人北九州生活科学センターでは、快適にプールをお楽しみいただくために、
水質検査を通してプール水の衛生管理のお手伝いをしています。
今回は、プール水の検査項目と各項目の基準値等についてお知らせ致します。
 項目 : 水素イオン濃度 (pH) 基準値 : 5.8以上8.6以下 説明 : pH7.0(中性)付近が良いとされています。数値が大きいとアルカリ性、小さいと酸性を示します。 項目 : 濁度 基準値 : 2度以下 説明 : 水の濁りの度合いを数値で表したものです。水質基準は、視野確保のために、肉眼でほとんど透明と認める限度です。 |  項目 : 過マンガン酸カリウム消費量 基準値 : 12mg/L 説明 : 水に溶け込んでいる汚れの基準です。 水質汚染を判断するうえでの重要な指標です。プール水中の有機物の多くは入泳者が持ち込む汚れ成分になります。 項目 : 遊離残留塩素 基準値 : 0.4mg/L (1.0mg/L 以下が望ましい) 説明 : 塩素消毒の指標です。感染症などを予防するなど、衛生管理上重要となります。 |
 項目 : 大腸菌 基準値 : 検出されないこと 説明 : 糞便等の汚染の指標です。遊離残留塩素が確保されていれば、検出されることは少ないです。 項目 : 一般細菌数 基準値 : 1ml中 200コロニー以下であること 説明 : 細菌汚染の指標です。屋外プールでは、落ち葉や周辺からの土壌にも付着している菌です。遊離残留塩素濃度が保たれていなければ、頻繁に検出されます。 |
 項目 : 総トリハロメタン類 基準値 : おおむね 0.2mg/L 以下が望ましい 説明 : 消毒剤の塩素と有機物が反応して生成するものです。検査は、水温が高く遊泳者が多い時期に1回以上となります。 (健発第0528003 号:遊泳用プールの衛生基準について) |
 プールの水質管理について プール(施設)を管理する上で、プールでの感染病を防ぐために遊離残留塩素濃度の管理が重要となります。塩素剤が適切に追加されていなければ、入泳者が急に多くなったときには、汗や垢などにより短時間で消費されますし、天候によってもその消費スピードは増します。機械による自動管理を過信することなく適切に管理を行うことが必要です。 プール(施設)を介してひろがる感染症 ・咽頭結膜熱(プール熱) : 発熱、咽頭痛、結膜充血 ・流行性角結膜炎(はやり目) : 眼けん充血、浮腫、流涙 ・手足口病 : 口腔・手掌・足底などの水泡 このほかにも、プール(施設)での感染症はたくさんあります。プール(施設)で病気に感染しないために次のことに注意をしましょう。 ・ 傷口や下痢があったり、病気にかかっているときは、プールに入らない。 ・ プールに入る前やトイレ利用後は、シャワーでしっかり身体を洗う。 ・ タオルの貸し借りをしない。 ・ 水の中でつばを吐いたり、水を飲み込まない。 |
 以前は、プール水の浄化施設が無いために、体の汚れで直接プールの水質を悪化させることのないように入泳前に腰洗い槽が使用されてきましたが、近年は循環式ろ過装置や消毒薬の自動注入装置の普及により腰洗い槽も使われなくなったようです。 気温が高くない日など、シャワーの中を駆け足で走りぬける子どもたちを見かけますが、これでは水質はすぐに悪化してしまいます。 プールに入る前やトイレを利用した後に腰洗い槽につかったりシャワーなどで充分に身体を洗うことでプール水汚染の軽減がはかられるので、設備を保有するプール(施設)では積極的に腰洗い槽を使用することをお薦めします。 最後に、プール水の水質検査は、プールの使用期間中に使用日数の積算が30日を超えない範囲で少なくとも1回以上行って下さい。総トリハロメタンについては、使用期間中に1回以上適切な時期に測定を行います。 暦の上では秋ですがまだまだ暑い日が続きます。プールで涼むなどして健康管理に充分にお気をつけ下さい。 最後までご覧いただきましてありがとうございました。 |
|
|
水の話よくある水のトラブルQ&A2012-04-06